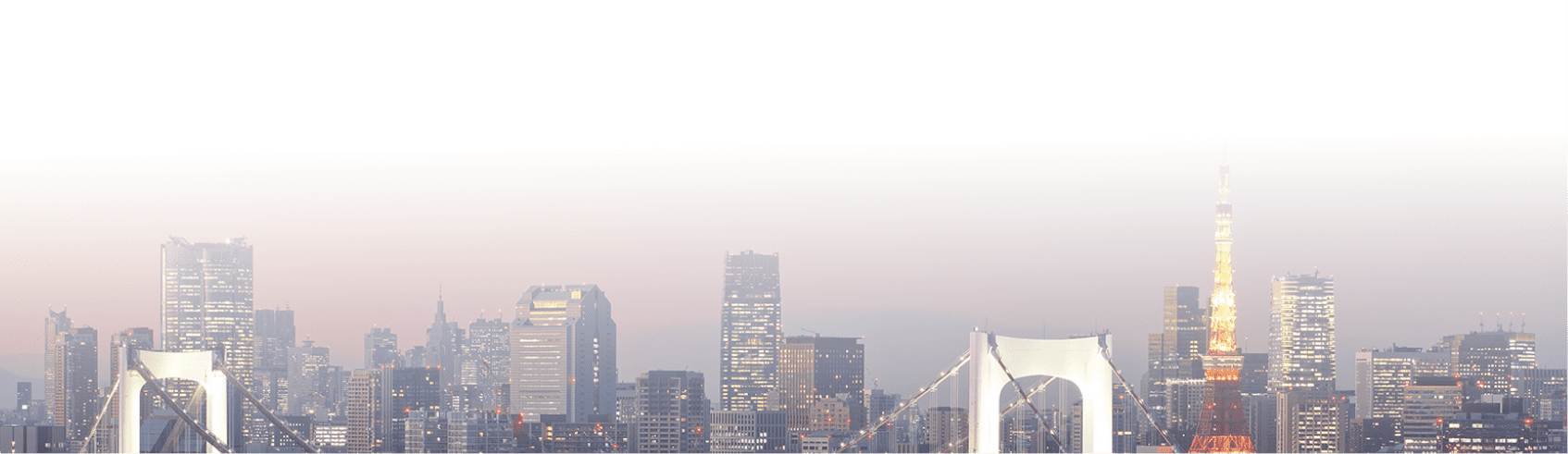外国人技能実習生制度を活用し、外国人材の雇用サポートで企業の人手不足を解消し未来を創造
昨今、企業の人手不足解消を目指して外国人技能実習生の受け入れが進んでいます。外国人技能実習生を受け入れる制度にはさまざまな規定や運用方法があり、実際の導入には複雑な手続が伴います。本記事では、外国人技能実習生の制度について、背景や運用の仕組み、企業が直面する課題に加え、実際の受け入れ方法やサポート体制について解説します。
本記事は「外国人技能実習生の受け入れを考えているが、どこから始めれば良いか分からない」「制度に関する問題点や、実務的な対応方法を知りたい」と考える方に向けて、必要な情報をまとめています。フィリピン人材を活用した採用方法を含め、スムーズに実習生を受け入れるためのポイントをお伝えします。
技能実習制度創設の背景と意義

技能実習制度は、開発途上国等の経済発展を担う人材育成を目的として、1993年に創設された制度です。技能実習制度は、日本で培われた技能、技術、知識を開発途上地域等への移転を通じて、国際協力を推進する役割を担っています。
制度創設までの経緯
技能実習制度の前身は、1960年代から始まった海外技術者研修制度です。当初は研修制度として運用されていましたが、より実践的な技能移転の仕組みが必要とされ、1993年に技能実習制度が創設されました。その後、2017年には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、現在の制度的枠組みが確立されました。
制度の基本理念
技能実習法では、技能実習の基本理念として以下の点が定められています。
技能実習は、労働力の需給の調整の手段ではならず、技能等の適切な習得、習熟または熟達のために整備され、かつ、実施する活動として行われなければなりません。
技能実習は、技能実習生が技能実習に専念できるようにするため、技能実習生の保護を図る体制が確立された環境で行われなければなりません。
制度の目的と期待される効果
技能実習制度の目的は、開発途上国等への技能移転による国際協力です。
技能実習生は日本の産業現場で実践的な技能、技術、知識を習得します。習得した技能等は、母国の経済発展に役立つ実践的なものとして選定されています。
技能実習生は日本での実習期間中、日本の産業現場における管理手法や生産方式、品質管理などについても学べます。実習で得た知識は、母国での産業発展への貢献が期待されています。
技能実習対象職種
技能実習制度で認められている職種は、開発途上国等の経済発展に役立つものとして選定されています。製造業、建設業、農業、漁業、食品製造業などの多岐にわたる職種が対象となっており、それぞれの職種について具体的な技能実習計画を作成する必要があります。
合同会社フィリピン投資研究所では、フィリピン人材の技能実習としてKENJIMIN日本語教育センターで日本語教育と、技能実習に必要な各種手続の代行サービスを提供しています。技能実習制度の目的である技能移転が行われるよう支援しています。
技能実習制度の運用の仕組み

技能実習制度は、技能実習法に基づいて厳格に運用されています。本章では、制度の運用の仕組みについて解説します。
受け入れ形態の種類
技能実習制度には、主に2つの受け入れ形態があります。
1つ目は「団体監理型」と呼ばれる形態です。事業協同組合や商工会等の監理団体が技能実習生の受け入れを監理する形態です。監理団体は、実習実施者である企業への定期的な監査や指導、技能実習生への相談対応などを行います。
2つ目は「企業単独型」と呼ばれる形態です。日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を技能実習生として受け入れる形態です。
技能実習の段階と期間
技能実習制度は、段階的に技能習得を進める仕組みです。
技能実習1号は、入国後の1年間が該当します。技能実習1号の期間は基礎的な技能等の習得を行います。入国後の講習期間(2か月以上)も期間に含まれます。
技能実習2号は、2年目から3年目の期間です。技能実習2号の段階では、実践的な技能等の習熟を図ります。技能実習2号に移行するためには、技能検定基礎級等の実技試験および学科試験に合格する必要があります。
技能実習3号は、4年目から5年目の期間です。技能実習3号の段階では、高度な技能等の習熟を図ります。技能実習3号に移行するためには、技能検定3級等の実技試験および学科試験の合格が必要です。
入国後の講習
技能実習生は入国後、実習実施先での実習の前に講習を受講する必要があります。講習では以下の内容を学びます。
日本語教育
実習を行う上で必要な日本語能力を身につけます。合同会社フィリピン投資研究所のKENJIMIN日本語教育センターでは、技能実習に特化した日本語教育プログラムを提供しています。
技能実習制度に関する法的保護に必要な情報
労働関係法令に関する知識など、技能実習生の権利を守るために必要な知識が学べます。
日本での生活一般に関する知識
日本の生活習慣、公共サービスの利用方法、災害時の対応など、日本で生活する上で必要な知識を学びます。
技能実習計画の認定
技能実習を行うためには、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。技能実習計画には以下の内容を記載します。
- 技能実習の目標および内容
- 技能実習の実施期間
- 技能実習を行う事業所の所在地
- 技能実習生の待遇
- 技能実習の指導体制
- その他技能実習の適正な実施を確保するために必要な事項
技能実習生の保護
技能実習生は、日本の労働関係法令による保護を受けます。具体的には以下の権利が保障されています。
- 労働基準法に基づく労働時間や休憩、休日の保障
- 最低賃金法に基づく賃金の保障
- 労働安全衛生法に基づく安全衛生の確保
- 労働者災害補償保険法に基づく補償
- 健康保険法および厚生年金保険法に基づく社会保険の適用
合同会社フィリピン投資研究所では、法令に基づく手続が行えるよう、企業様向けに手続の代行サービスを提供しています。
外国人技能実習生を活用した地域社会への貢献
外国人技能実習生制度は、企業の人手不足解消だけでなく、地域社会においても多くの貢献を果たしています。技能実習生が地域のイベントやボランティア活動に参加することで、地域住民との交流が進み、多文化共生の促進に寄与します。
また、技能実習生が地元の産業に従事することで、地域の経済活性化にもつながります。一方で、生活環境や言語の壁など、受け入れ地域の支援が不可欠な課題も存在しています。地域全体が一体となり、受け入れやサポート体制を整えることで外国人材の力を最大限に活用し、持続可能な地域社会の実現を目指すことが重要です。
実習生の労働環境における課題と企業側の実務的な困難点
技能実習生の受け入れにおいては、労働環境の整備と実務面での対応において、企業はさまざまな課題に直面します。本章では、主な課題と対応について解説します。
労働関係法令の遵守に関する課題
技能実習生は日本の労働関係法令によって保護される労働者として位置づけられています。企業は以下の事項を確実に実施する必要があります。
労働時間管理については、法定労働時間の遵守、適切な休憩時間の確保、休日の付与が求められます。時間外労働や休日労働を行う場合は、労使協定(36協定)の締結と届出が必要です。
賃金管理においては、最低賃金法の遵守はもちろん、同種の業務に従事する日本人従業員と同等以上の賃金支払が必要です。また、割増賃金の計算や各種手当の支給など、適切な賃金計算と支払管理が求められます。
安全衛生管理の課題
労働安全衛生法に基づく安全衛生教育は、技能実習生が理解できる方法での実施が必要です。特に以下の点に注意が必要です。
作業手順や安全確認事項について、技能実習生の母国語または理解可能な言語での説明資料の作成が必要です。定期的な安全衛生教育も、技能実習生が理解できる方法での実施が必要です。合同会社フィリピン投資研究所では、KENJIMIN日本語教育センターを通じて、安全衛生に関する基本的な日本語教育を実施しています。技能実習生が安全衛生教育を適切に理解できるよう支援しています。
在留資格管理の実務的課題
在留資格に関する手続は、企業にとって重要な実務的課題です。具体的には以下の手続が必要です。
- 在留資格認定証明書の取得手続
- 技能実習計画の認定申請
- 在留期間更新許可申請
- 技能実習の各段階における移行手続
生活支援に関する課題
技能実習生の生活支援も重要な課題です。以下の事項について、適切な対応が必要です。住居の確保と管理については、技能実習法で定められた基準を満たす施設の用意が必要です。また、水道・光熱費の管理や設備の維持管理など、継続的な対応が求められます。
医療機関の受診支援では、健康保険の手続や、必要に応じた通訳の手配が必要です。また、定期健康診断の実施と結果に基づく適切な措置も求められます。
日本語教育・コミュニケーションの課題
技能実習生との円滑なコミュニケーションは、実習を成功させる上で極めて重要です。特に以下の点に注意が必要です。
業務指示や技能指導を行う際は、技能実習生の日本語理解度に応じた適切な説明方法が必要です。また、安全に関する指示や緊急時の連絡については、確実な意思疎通が求められます。
KENJIMIN日本語教育センターでは、職場でのコミュニケーションに必要な実践的な日本語教育を提供しています。また、定期的なフォローアップを通じて、技能実習生の日本語能力の向上を支援しています。
書類作成・記録管理の課題
技能実習制度では、さまざまな記録や報告書の作成・保管が求められます。主な書類には以下のものがあります。
- 技能実習計画に基づく実習の進捗状況記録
- 技能実習生の出勤簿・賃金台帳
- 技能実習生の技能習得記録
- 定期的な監査のための各種報告書
制度活用のポイント
技能実習制度を効果的に活用するためには、以下の点に注意が必要です。
まず、実習計画の作成段階から、技能移転の目的に沿った計画が重要です。実習生の技能レベルや日本語能力を考慮し、段階的な技能習得が可能な計画を作成しましょう。
実習生の受け入れ前から、社内の受け入れ体制の整備も重要です。技能実習指導員や生活指導員の選任、実習生との円滑なコミュニケーションを可能にする体制の構築が必要です。
合同会社フィリピン投資研究所では、フィリピン人技能実習生の受け入れに関するワンストップサービスを提供しています。実習生の選考から入国後の支援まで、企業の皆様の負担を軽減し、効果的な技能実習の実施をサポートいたします。
外国人技能実習生・特定技能生・労働者に関するコラム
- 外国人技能実習生を受け入れるには?手続きから注意点まで徹底解説
- 外国人の技能実習生を受け入れるには?制度概要・手続・注意点まとめ
- 技能実習生制度見直しで企業はどう変わる?外国人受け入れの影響やポイント
- フィリピン人技能実習生の受け入れ手続きを徹底解説!
- フィリピン人技能実習生の評判は?フィリピン人の性格や仕事の実態を紹介
- フィリピン人の特定技能生の受け入れを成功させる支援機関の活用ガイド
- フィリピン人の特定技能外国人の受け入れ手続き・費用の完全ガイド
- 企業の成長戦略としての外国人労働者の受け入れのメリットと活用法
- 外国人労働者受け入れに活用できる補助金制度
- 技能実習生の雇用トラブル事例と効果的な予防・対策法
外国人技能実習生制度の専門家、合同会社フィリピン投資研究所
| 会社名 | 合同会社フィリピン投資研究所 |
|---|---|
| 代表社員 | 牧山 あけみ 笹沢 安基子 |
| 住所 | 〒379-2301 群馬県太田市藪塚町426-1 スペースタウン駅前 105 |
| TEL | 0277-47-6973 |
| FAX | 0277-47-6974 |
| メール | akemi@prii-llc.com |
| URL | https://www.prii-llc.com/ |
| 事業内容 |
・外国人就労支援事業 ・教育、学生支援事業 ・国際ビジネス支援事業 |